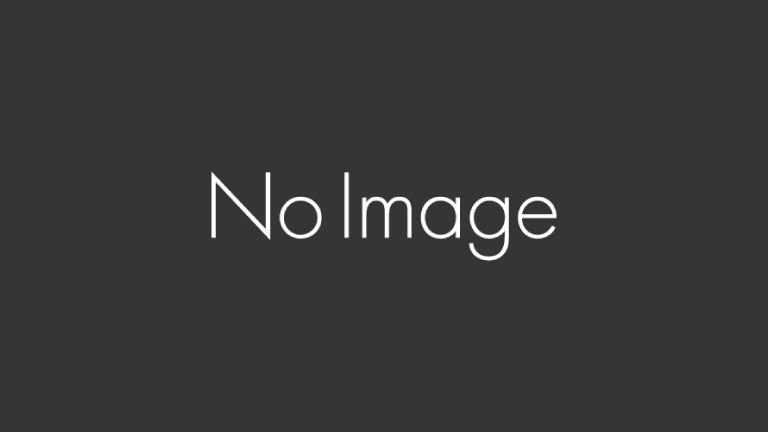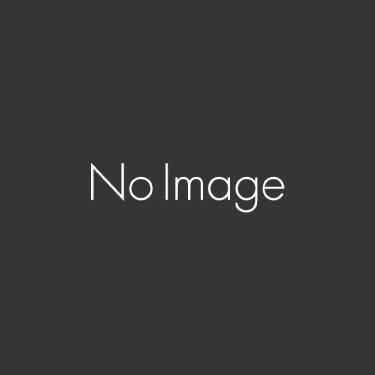今回はカルボニル基の反応を見ていこうと思います。
カルボニル基が反応する部位は3つあります
酸素(求核性、塩基性)
炭素(求電子性)
アルファ炭素(カルボニル基の炭素に隣接する炭素)
性質の違うそれぞれの部位が反応を起こしてゆきます。
イオン的付加
カルボニル基が極性を帯びているので、電荷に偏りのある分子とイオン的に付加反応します。求電子的な炭素は求核剤と反応し、求核性、塩基性のある酸素は、求電子剤やプロトンと反応します。
塩基性の強い求核剤の場合
塩基性の強い求核剤である有機金属反応剤(RMgX)や、ヒドリド反応剤(NaBH4)を加えると、カルボニル基は反応してアルコールを生成します。
塩基性の弱い求核剤の場合
上の塩基性の強い求核剤の場合の反応では、不可逆反応になるが、塩基性が弱い求核剤(Nu-H(例 Nu: OH OR SR NR2))の場合、平衡状態となり、適切な条件下にすればどちらにも進行させることができるようになる。
この反応酸素は、炭素への求核付加から始まるか、酸素へプロトン化から始まるかの2種類の反応経路がある。塩基性条件か酸性条件かで変わってくるので、違いをしっかりおさえておきましょう
塩基性条件(Nu-が先に付加)
求核剤Nu-HのNu-が、正に帯電している炭素を攻撃し、二重結合が開裂。そうしてできたO-にプロトンH+が攻撃し、求核付加が完了します。
結果的に、-Nuと、-OHが付加したことに注目すると理解するのが早いのではないでしょうか。
このとき塩基性条件なのは、酸性でプロトンがある場合には、求核剤に対し、プロトンの攻撃があり、それで反応が完結してしまうからです。
酸性条件(H+が先に付加)
C=Oが分極していることにより生じる酸素原子上での負電荷に溶液中に多量に存在するプロトンが配位すると、炭素の求電子性が増し、非常に反応性の高いカルボニル基へと変化する。その炭素の部位に求核剤Nuが付加することで反応は完結します。
このとき酸性条件下であるのは、水素のプロトン化が酸性条件でないと起きづらいからです。
これらの反応では、炭素がカルボカチオン的な性質を持っているので、結合している炭素基が多いほど、また電子吸引基であるハロゲンなどが結合していないほど、安定化する。そのため、電子吸引基を持つカルボニル基ほど反応性は高く、炭素基など電子供与性の基がつくと、反応性は低くなる。
ヘミアセタールの生成
先ほどの話に引き続き、アルデヒド、ケトンへの付加反応として、NuHの部分にROH、つまりアルコールが入った場合を考えてみましょう
このときも同様にカルボニル基に-Nu(-OR)と-OHが付加した分子ができあがります。
この構造をヘミアセタール構造といいます。
ヘミアセタールは、平衡がもとのカルボニル側に偏っているため、純物質として単離することができません。
アセタールの生成
ヘミアセタールは、カルボニル基にアルコールが付加したものですが、このときアルコールが過剰にある場合を考えてみましょう。
まず第一段階として、カルボニル基に初めのアルコールが付加します。これは先ほどの生成と同じで、ヘミアセタールができあがります。
このとき、ヘミアセタールの-OH基にさらにH+が配位します。すると、これは水(H2O)の構造を持ち、脱離基として優れた力を持っているために、脱離し、そこにもう一分子のアルコールが付加します。すると、-OHと-ORの構造が、-ORと-ORの構造へと変化します。
これらの反応も可逆的であり、アルコールの量や、水の量に依存して平衡を偏らすこともできます。
このとき、H+の付加が反応の開始に寄与するので、酸性条件でなければ反応はおこりません。
逆に言えば、アセタールは酸性下では不安定ですが、塩基性・中性条件では比較的安定して存在することができます。
さらに言えば、アセタールはヘミアセタールとは違い、純物質として単離することができます。
環状アセタール
上記のアセタール生成で用いた二分子のアルコールを一分子に2つの-OH基を持つジオール類に変えてみるとどうなるでしょうか?
二分子続けてカルボニル炭素に付加することによって、環状のアセタールを形成することになります。
アセタールは、酸性条件以外では反応性が低いということを活かして保護基としての役割をもちます。
特に、環状アセタールでは、生成エンタルピーなどの理由により非環状のアセタールよりも安定で、保護基として大きな働きをします。
チオアセタール
チオール基(-SH)は水酸化基(-OH)と非常に似た性質で、カルボニル基に対しても同様の反応をみせ、チオアセタールを生成することができます。
-SHの-OHとの違いは、生成されたチオアセタールが、酸触媒中でも安定であるということです。
この違いは、同一分子中のカルボニル基を区別するときに有効活用できます。
加水分解するには、塩化水銀が必要になります。
さらに、細かな知識ですが、Raneyニッケルを用いるとチオアセタールが脱硫されて、炭化水素になる。これでカルボニル基がメチレン基にまで変換されます。
ヘミアナタール
今度は-OHや-SHの代わりに、-RNHH(-RNH2)を用いる場合を考えましょう
これまたヘミアセタール同様に-OHと-NHRができます。
ヘミアナタールの-OH基にプロトンが付加するとき、普通のヘミアセタールの場合は、これからアセタールへと変化したりしますが、窒素が含まれている場合には、N=C二重結合を生成し、イミンを生成します。
イミンは、アルデヒドやケトンの特定に役に立ちます。
あるアミンとアルデヒドやケトンが縮合してできた物質は、結晶性が高く、特定の融点を持つイミンを生成します。これらの融点の違いにより、アルデヒドやケトンの特定をすることができます。
第二級アミンの場合も同様の反応が起き、この場合はイミンではなく、エナミンが生成されます。
シアノヒドリン
今度は、NuHのNuにCNが入った場合を考えます。
予想通り、-CNと-OHが付与した形になるのですが、ここで問題なのは、用いるHCNが有毒であるということです。これはとても危険なので、HCNの代わりに、NaCNなどのシアン化物塩を入れ、強酸で遊離させることによって、シアンヒドリンを生成します。
反応のファーストステップは、正の電荷を帯びたカルボニル炭素に、負の電荷を帯びたシアン化物イオンの炭素が攻撃をし、二重結合が開裂。カルボニル基だった酸素の部分に、もう一分子のシアン化水素のプロトンが配位し、反応は完結します。
まとめ
カルボニル基が反応する部位は3つ。
カルボニル基は求核付加を起こし、二重結合を開裂させ、アセタールやチオアセタールなどを生成させます。
環状アセタールは保護基として有益ですが酸触媒に弱い。チオアセタールは酸触媒に強い。