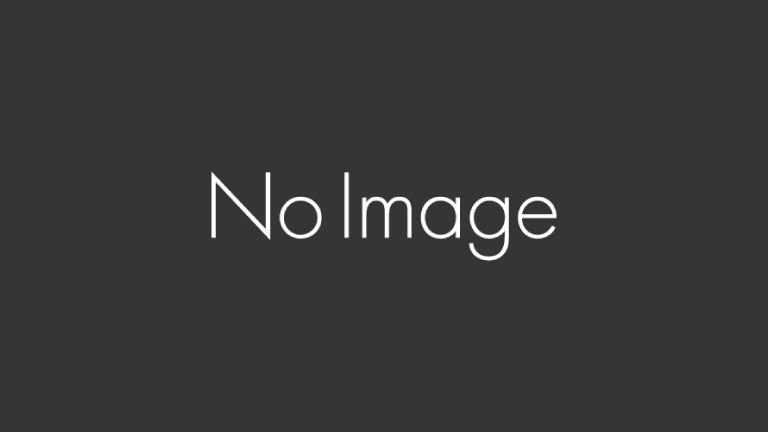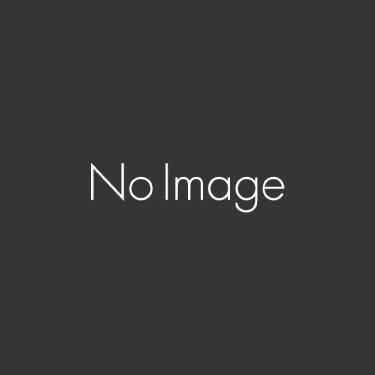シュレディンガー方程式が正確に適応できるのは水素原子(原子核一個と電子一個)の場合でした。
そこで、シュレディンガー方程式をヘリウム原子(原子核一個と電子二個)の場合を考えてみます。
このとき、近似法を用いるのですが、この近似には二種類あります。
摂動法
変分法
それでは、実際にみていきましょう
摂動法
ある方程式をとくのが難しいとき、その方程式よりも簡単にした方程式が解けることがわかっているならば、その解を利用して元の複雑な方程式を解く方法を摂動法といいます。
簡単な関数に微小の項が加わって複雑になる場合、この微小の項を摂動項と呼び、これを加えることによってより近い近似解を得ることになります。
具体的には、ヘリウムでは原子核のまわりに2個の電子がありますから、その2個の電子の間に働く相互反発力がここでの摂動項になります。
ハミルトニアンでいうと、水素原子の場合のシュレディンガー方程式は、
H0Ψ=EΨですが、
摂動項λH’が入る場合を考えると、
H=H0+λH’
に変わります。
このλHは電子の間に働く相互反発力から生まれるものであり、λを極めて微小な値であると考えます。
ここから数式が多くてわかりづらくなるので、一度出てくる文字を整理します。
H0 : 無摂動状態でのハミルトニアン(水素原子に対するハミルトニアン)
H : 摂動項が加わった状態でのハミルトニアン
H’ : 摂動項に寄与するハミルトニアン
さらに固有関数
Ψ(0)は、無摂動状態を表し、Ψ(1)は一次の摂動項。Ψ(2)は二次の摂動項となります。
Ψは一つではないので、それを表すために下付きの数字を用いて、
Ψ1 を基底状態、Ψ2を第一励起状態、Ψ3を第二励起状態を表すと決めます。
表記の仕方が一通りわかったところで、もう一度先ほどのシュレディンガー方程式を登場させましょう。
HΨn =EnΨn
ここからが摂動法の本番です。
摂動項は無摂動項(元の項)に比べてとても小さいです。ですから、そこから生じる固有関数や固有値の変化の値も極めて小さい考えられます。
λ=0ならば、元の無摂動項と一致することも考えると、次のような表し方ができます。
Ψn =Ψn(0)+λΨn(1)+λ2Ψn(2)+λ3Ψn(3)+・・・
En =En(0)+λEn(1)+λ2En(2)+λ3En(3)+・・・
つまり、ΨnとEnはそれぞれ無摂動の項Ψn(0), En(0)によってそのほとんどが決まります。
そこから一次の摂動項、二次の摂動項という風に足していくことで、修正していくという流れです。より、細かな項を足していくことで、近似の精度がどこまでかを理解することができます。
例: 一次の項まで取り入れたときのシュレディンガー方程式
一次の項まで取り入れるので
H=H0+λH’ Ψn =Ψn(0)+λΨn(1) En =En(0)+λEn(1) です。
これをシュレディンガー方程式HΨn =EnΨn に代入すると
(H0+λH’)(Ψn(0)+λΨn(1))=(En(0)+λEn(1))(Ψn(0)+λΨn(1))
そして少々面倒臭いが、この式を展開しλの次数ごとに整理をします。
H0Ψn(0) – En(0)Ψn(0) +λ(H0Ψn(1)+H’Ψn(0)-En(0)Ψn(1)-En(1)Ψn(0))+λ2(H’Ψn(1)-En(1)Ψn(1))=0
λ=0のとき、これは当然成り立ちます。(無摂動のシュレディンガー方程式と同じ)
λ≠0のとき、この方程式が成り立つ条件を考えます。
このときλnでくくった括弧の中身が全て0でなければなりません。(恒等式的に)
つまり、λ一次の項より
H0Ψn(1)+H’Ψn(0)-En(0)Ψn(1)-En(1)Ψn(0) =0
λ二次の項より
H’Ψn(1)-En(1)Ψn(1)=0
という二つの方程式が得られます。
一次の項より得られた方程式をまずみてみましょう。
H0Ψn(1)+H’Ψn(0)-En(0)Ψn(1)-En(1)Ψn(0) =0
ここからが難所です。
Ψn(1) というのはおさらいですが、一次の摂動項です。
これを無摂動ハミルトニアンH0 の固有関数系で展開します。
Ψn(1) =ΣaiΨi(0)
どうしてこんな操作をするかはさておき、この展開ができることがわからない方は、一度、量子力学の前提に遡ってみてください。無摂動ハミルトニアンの固有関数系が完全系を作っていることを利用しています。
そして、これを H0Ψn(1)+H’Ψn(0)-En(0)Ψn(1)-En(1)Ψn(0) =0に代入します。
すると、H0ΣaiΨi(0)+H’Ψn(0)-En(0)ΣaiΨi(0)-En(1)Ψn(0) =0
このとき着目して欲しいのは、今の操作で、波動関数の一次の摂動項が消え、En(1)以外は無摂動項だけになっています。
ということは、En(1)=の形に直したとき、右辺にくるのは無摂動の項のみとなります。
これは、今までの波動関数の解き方で処理できるということを意味します。
では実際にEn(1)=の形に直してみましょう。
このとき、工夫するポイントが一つあります。それは、規格直交性を利用して式を簡単にすることです。両辺にΨn(0)の共役な複素数Ψn(0)❇︎をかけ、積分をします。
(計算過程)
En(1)=∫Ψn(0)❇︎H’Ψn(0) dξ
これを∫Ψn(0)❇︎H’Ψn(0) dξ=H’nn と表記することにする。
よってEn(1)=H’nn
これが意味していることは、エネルギーの一次の摂動項はハミルトニアンの摂動項部分H’の期待値に等しいということです。
En =En(0)+λEn(1)でしたから
En =En(0)+λH’nn H’nn =∫Ψn(0)❇︎H’Ψn(0) dξ
En(0)=∫Ψn(0)❇︎H0Ψn(0) dξであることを考えると、このようにもかける
En=∫Ψn(0)❇︎[H0+λH’]Ψn(0) dξ
すなわち、摂動の一次までのエネルギーはEnは、摂動を含むハミルトニアンの、無摂動の波動関数による期待値に等しいと言えます。